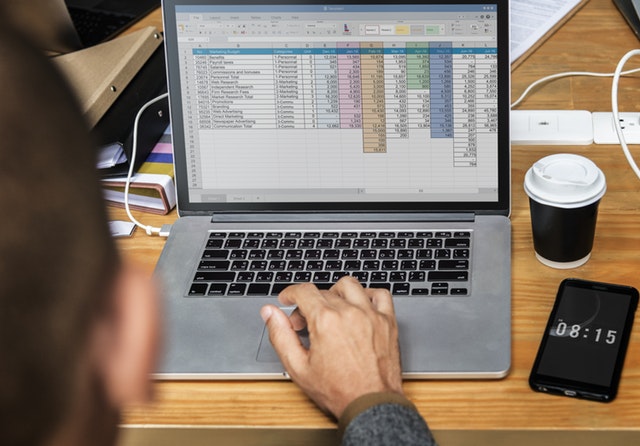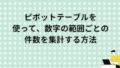私は、業務改善系の記事が大好きです。
先日読んだ、この記事が印象的でした。
サイボウズなのに毎日残業──激務の採用チームを救ったのは「スクラム」だった | サイボウズ式サイボウズといえば業務改善プラットフォームであるkintoneを公開していたり、
多様な働き方を推進していることで有名ですが、
実際に働いている方々は結構、激務です。
その中でも、採用チームはすごく忙しいんだろうなと、
前から思っていたのですが、やっぱりそうだったみたいです。
サイボウズ社の柔軟な働き方の大前提となるのは、
社員の経営理念に対する共感や、目的へのコミットメント、
社員が自立していることなど、目に見えないものが多いので、
「これらを見極めなくてはいけない採用チームって大変そう……」
って感じていました(^_^;)
でも、やっぱりサイボウズらしいなと思う所は、そんな激務の中でも、
採用チームが改善を目指したという点ですね。
業務改善というのは、手間も時間もかかります。
激務の中で時間を作り、チームで取り組むというのは、
メンバーにとっても負担になります。
普通のチームが業務改善できない大きな理由は、ここにあります。
忙しいのに、更に、自分の手間と時間を使って面倒なことをやるなんて
ゴメンなのです。
だからこそ、仲間だとか、大きな目的へのコミットメントがなければ
できないことです。
私が特に印象的だったのは、記事の中のこの画像。

矢印部分です。
「夕食など、家族の生活時間とずれる」
この、個人の価値観が表明されているという点が素晴らしい。
これが示されていることからも、採用チームにおける心理的安全性が高いという
ことが伺えます。
※心理的安全性とは、自分の意見を安心して表明できる状態のことです。
最近の研究では、心理的安全性の高さこそが、チームワークの強さに
直結すると言われています。
個人の価値観を尊重した上で、チームとしてできる解を目指す。
その姿勢からも、チームワークの強さが伺えます。
そしてこの記事を読んで私が思ったこと、それは……
「KPTとスクラムってなんだろう??」でした。
ヽ(・ω・)/ズコー
KPTとは何か
KPTとは、「指導されることがなくても、自律的に改善していけるようにする」
メソッドです。
- Keep(良かったこと、続けること)
- Problem(悪かった事、やめること)
- Try(次に挑戦すること)
の3つで構成されていて、
日々行ったことを、このフレームワークに当てはめます。
【徹底解説】正しい「KPT」が仕事の成果を生み出す!進め方のコツ、現場の事例を紹介
https://seleck.cc/kptより
PDCAにも似ていますが、KPTはチームで使うことを前提としているので、
よりシンプルに、やったことが良いのか悪いのか、見える化します。
運用は、
ホワイトボードやノートにフレームを書き、付箋を貼っていく、
Trelloのようなカンバン式のアプリを使う、
といった方法があります。
上記のサイボウズの記事では、kintoneアプリを利用していました。
KPTは、チームで1~2週間ごとにレビューします。
取るべき行動だけが残っていくので、
どんどんチームの行動がブラッシュアップされていきますね!
スクラムとは何か
スクラムとは、ソフトウェア開発手法のひとつです。
優先順位の高いものから、短期間で開発できるという強力なメリットがあります。
スクラムとは(オージス総研HPより) https://www.ogis-ri.co.jp/column/agile/agilescrum01.html
スクラムの軸は、「スプリント」という開発期間です。
数週間程度という短期間に、1つのプログラムを作ります。
スプリントにあたっては、
スプリント計画という、開発目標を作成します。
スプリント計画の元になるのは、プロダクトバックログであり、
これは優先順位でソートされた、やることリストです。
やることリストの中から優先度の高いものを、数週間の間に作るイメージです。
スプリントの結果、生み出されたプログラムはプロダクトオーナーという
責任者によってレビューされます。
プロダクトオーナーはプログラムを評価し、
バックログのやることリストや優先順位を再構成します。
プロダクトオーナーが再構成したリストを元に、
開発チームがまたスプリントを行う……。
これがスクラムです。
優先順位の高いものから着手できて、短期間で一つの目標に集中するので、
チームがダレにくく、「アレ?いま何やらなきゃいけないんだっけ……?」
といったことになりにくいです。
おわりに
サイボウズ式の記事を見ていると、チームで働くためのメソッドが
たくさんあって勉強になります!
今まで業務改善とかそこそこやってたんですが、実はスクラムとかKPTといった、
システム系の会社が当たり前にやっていることを全く知らなかったので、
今回の記事はいいきっかけになりました!
こんなに良い仕組みを使わないなんて、もったいないですよね。
自分の環境でやってみたいと思います!まずはなんでもやってみることから!