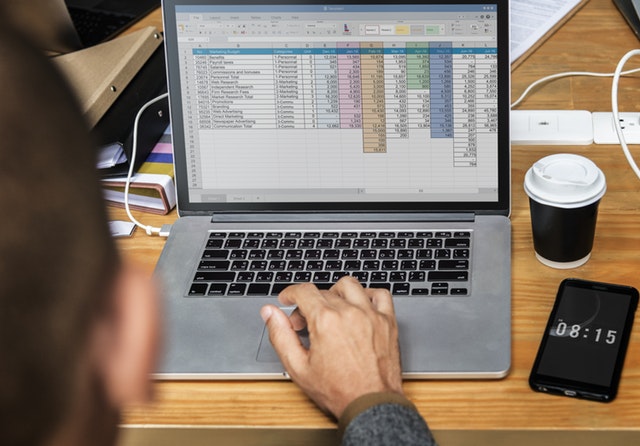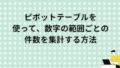今日は10月に読んだ本のまとめです
こんにちは、おぎです。
2019年10月に読んだ本は9冊でした。
四半期決算やら子どもの運動会がある中での読書でしたが、
・付箋を使ってページ間の往復を楽にした
・ノートの書き方を変えた(麹町中学校式)
といったことでリズムよく読み進められました。
こういうのは勢いを止めないのがコツ(๑•̀ㅂ•́)و✧
10月のベスト!『学校の「当たり前」をやめた。 ― 生徒も教師も変わる! 公立名門中学校長の改革 ―』
10月のベストは、文句なしに『学校の「当たり前」をやめた。
― 生徒も教師も変わる! 公立名門中学校長の改革 ―』です!
この本から感じるエネルギー量はホントに多い!
書いた人はどんな人?
この本は、千代田区の麹町中学校の校長である工藤勇一さんの本です。
期末テストや宿題の廃止をはじめとした学校の改革を進めていて、
その手腕が「カンブリア宮殿」などに紹介されるほど、勢いのある人です。
元々教育者としての意識が高く、子供に真摯に向き合う人物であることが
本を読むとわかります。
どんな本?
工藤勇一さんがどのように学校の制度改革を行ってきたのか。
それを解説したのが本書です。
どのように変えたか一言で表すなら、
「教育の最終目的を見直して、それに合致する手段を選んだ」
ということです。
工藤さんが考える学校の存在意義というのは、
「社会でより良く生きていけるようにすること」です。
非常に明確ですね。
この最終目的から考えれば、宿題も、期末テストも、厳しい服装や髪型の指導もいらない、じゃあやめてしまおう、というのが改革の内容です。
でもこれって、全然簡単なことじゃない。
長年みんなが当たり前だと思っていることばかりだから、
当然同僚である教師からも反発の声が出たりする。
工藤さんがスゴイのは、そんな時にもちゃんと、教育の最終目的を共有して、同じ方向に向かって一緒に考えたということ。
これは本当に、優れたリーダーの素質であるし、見習わなくちゃいけない姿勢だと思いました。
ホントに学ぶことの多い良書です。
ぜひ読んでみてください。



10月に読んだ本と感想
以下、読書メーターに投稿した私の感想です。
『教える技術』の内容はとてもタメになるけど実践が難しい!
・教えるとは、行動を正しいものに変えてあげること
・大切なものから順番に伝える
この2つだけでも押さえておきたいです。
教えてる時はわからなくなっちゃうけど。
10月の読書メーター
読んだ本の数:9
読んだページ数:2135
ナイス数:58



家族4人で4年間、世界中を旅した記録。旅の途中で感じたことが写真と共に1ページずつ綴られていて、世界の広さを感じることができます。どこに行っても、自然の偉大さは変わらないし、その中で人間の感じることや言葉が面白い。もっと自分の感性を大切にしたいと思いました。
読了日:10月31日 著者:高橋歩



会議の有効性を高めるために読了。 会議を有効にするためには、各参加者が立場に関係なく意見できることが重要です。 なんらかの課題を話し合う会議では、立場の違いによって見ているものが違い、言えること・言えないことが存在します。「会議冒頭で意見を紙に書くことによって、意見を言えるようにする」「課題を、どうすれば〇〇できるようになるか、という質問の形に変える」などの手順を踏むことにより、会議の参加者が問題解決の手順を共有できるようになります。この本を実践するなら、意思決定の権限がある少人数で行うのが良いでしょう。
読了日:10月31日 著者:大橋 禅太郎



ビジネスモデル構築の理解を深めるために読了。利益を出すには「儲かる仕組み」を作る必要があるという話です。 本書の軸となるのはいわゆるジョウゴの法則で、「おとり商品→リピーター化→本命商品を売る」というモデルです。ジョウゴのモデルを構築するには、他社がなぜ成功しているかを分析した上で、自社にあった戦略を立てる必要があります。この分析がなければ必ず失敗します。しかし、戦略が合っているかはやってみないとわからないので、致命的でない失敗を沢山することが成功の秘訣なのでしょうね。
読了日:10月29日 著者:髙井 洋子



自分のビジネスを持つために読みました。今まで「自分の肩書」に悩んでいましたが、この本をヒントに方向性を見つけられました。 本書は週末を使い「専門家」としてビジネスをするための本です。「どのように専門家と名乗るか」「営業はどうするか」「会社にバレないようにするには」といった手順が丁寧に解説されているので、内容を実践すると、ビジネスの形ができあがるようになっています。 本の内容を実践してみて、自分は●●の専門家だ、と名乗ることは勇気がいることだと分かりました。経験を積めば慣れていくのでしょうか……。
読了日:10月26日 著者:藤井 孝一



自分の働き方を決めたくて読了。本書は「ラットレースに巻き込まれない(消耗しない)ように働くにはどうすればよいか」を資本主義の構造から説明した本です。会社員の給料は、生活に必要な最低限の分しかもらえないので、「生活のコストを下げる」「ストレスを受けない仕事をする」「仕事からノウハウを蓄積する」ことで、元手が残るようにすることが大切です。 今の私にとって仕事から得るものは限られているので、副業で自分の資産を積みたいと思いました。
読了日:10月23日 著者:木暮 太一



読了日:10月22日 著者:石田 淳



教えるのが苦手なので読みました。教えるということが思っていたより奥深くて面白い!! 本書において、「教える」ということは、「望ましい行動ができるようにする」です。「結果に直結する重要な行動」について、優先度の高いもの、やらなくていいことも伝えます。行動できるようになったら、何回行ったか数えたり、その行動ができたらすぐに褒めるといったように、継続できる仕組みを作ります。特に、筋トレのように、すぐに成果が得られないものは、行動の後にすぐ「良い結果」を与えてあげることが大切。教える立場の人は、すぐに読むべき。
読了日:10月22日 著者:石田 淳



今年読んだ本の中でもベストです。工藤校長が行ったのは突きつめれば、「物事の目的を再定義して、それに合致しない作業や行動をやめた/変えた」ということですが、それが非常に大きな変化を生むことがわかります。なにより素晴らしいことは、工藤校長自身が、関係各所と交渉する際に簡単には諦めず、対話によって相手と目的を共有し、助けてもらうことができるということ。目的に対する熱意と、人を巻き込む力というものを感じさせる一冊でした。
読了日:10月20日 著者:工藤 勇一



本書は、婚活をしている女性向けに「どうすれば幸せな結婚ができるのか」について書かれた本です。 大切なことは「今の自分を好きになること」「”〇〇がなければ幸せになれない”と思わないこと」です。 等身大で今の状態を幸せだと思っていれば、良い人が目の前に現れた時に、自然と結ばれます。 僕は既婚男性なので、女性特有の感覚が記述された部分はピンとこないのですが、妻が等身大で幸せを感じられるように過ごそうと思いました。
読了日:10月04日 著者:高橋 ナナ
読書メーター
目指せ10冊。 11月も頑張っていきましょう。