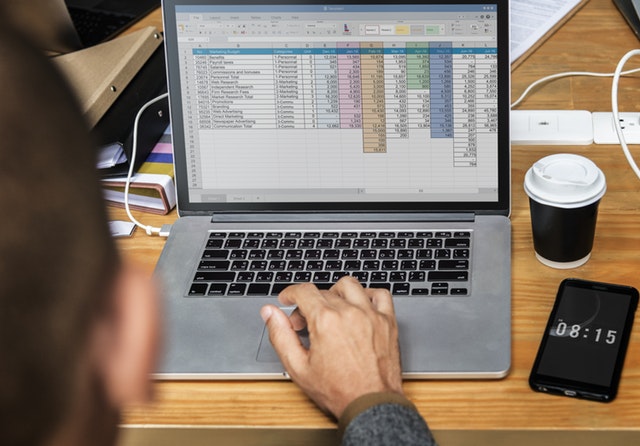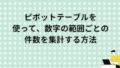『誰かの記憶に生きていく』(著:木村光希さん)の感想です。
- 死に向き合い、生き方を考えることが、死生観を磨く
- 具体的には、「死との距離感」と、「自分が何によって憶えられたいか」を意識する
- 死の喪失を受け入れることができなければ、前に進んでいくことができない。
そのために、葬儀や納棺の儀、一定期間ごとの集まりなどの儀式が必要。
死とどのように向き合って生きていくかは、誰にとっても避けられない永遠のテーマです。
僕もこのテーマに関する本を色々読んできましたが、多くの場合、
そこには「今日しか生きられないとしたらどう生きるか」とか、
「後悔のないように生きる」ということが書いていて、
頭ではわかっていても心が動かない。
なにか自分の心に響く本はないかと、ずっと探していました。
今回、「納棺師」という常に死の現場にいる方が書いた生き方の本を、
偶然見つけることができました。
この本を読んで、納棺のとき、残された人がどのような悲しみに包まれるのか、
残された人たちがどのように故人を語られるのかを通して、
より自分ごととして生き方の学びを得ることができました。
木村光希さんが書いた、『誰かの記憶に生きていく』です。
読んでいる間、特に、幼い子供の納棺、子を残したまま亡くなった
親の納棺のエピソードは涙なしでは読めませんでした。
ぜひ読んでみてほしい本なので、この本から大事だと思ったことを、今回は書いていきます。
死に向き合い、生き方を考えることが、死生観を磨く

本書のテーマは、”自分が迎えるであろう死を想定し、
逆算することで「どう生きるか」を真剣に考えるきっかけとする”ことです。
不確実なものが多すぎるこの世の中で、「誰もが死を迎える」ということだけは変わりません。
だからこそ、死をどこか自分とは関係ない、遠いところに考えるのではなく、
正面から死と向き合って生き方を考えることで、死を味方につけようというのが、
本書が伝えたいメッセージです。
死を考えることは、生を考えること。
生きる意味を問い、どう生きるかを考えること。
本書では具体的な考え方を2つ紹介しています。
死との距離感
木村光希さんは、「自分が6ヶ月後におくられるとしたら?」と、
死との距離感を意識することを書いています。
死との距離感を意識することで、「後悔しないためにどうするか」を考え、
心の動かないものに、時間を使わないようになります。
また、6ヶ月後に送られるのは自分でなく、他人も同じです。
だから、家族や仲間との何気ない時間も大切に感じます。
ちいさな幸せに気がつくことができるようになります。
スティーブ・ジョブズは「今日が人生最後の日なら、あなたはどう過ごすか」
という名言を残しましたが、木村さんにとってこれは短すぎたため、試行錯誤して
それで6ヶ月という期間がしっくりきたそうです。



僕も6ヶ月後に送られるとしたら、仕事は引き継げるところまで頑張って、行きたいところに行って、やりたかったこともやって、その後は家族と過ごす時間にしたいですね。6ヶ月あれば、なんとかできそうです。
6ヶ月というのは、自分のやりたいことをやりきるのにちょうど良い時間だと思います。
この「できそうだ」という感覚をもつのが大事かなだと思いました。
自分は何によって憶えられたいか
自分がいなくなったとき、残された人たちにどう憶えられたいか、
それを考え続けることが、より充実した日々を生きるためのヒントになります。
木村さんは納棺の現場で、故人がどのように憶えられているのかを常に聞いています。
「どのように憶えられるか」には、その人らしさがでます。
「残された人たちの記憶だけが、自分と世の中をつなぎとめる」と本書にも書いてありますが、
”どのように記憶されるか”は、”自分がいなくなった後の自分そのもの”です。
僕だったら、「優しい人だった」と憶えてもらいたいです。
これは自分の中で欠かせない「自分らしさ」です。これは深めていきたいですね。
死の喪失感をどのように受け入れるか



死の喪失感と向き合い、故人が残してくれたものを憶え、
それを自分の人生に活かしていくことで人生はより豊かになります。
この死の喪失感を受け入れていくステップのことをグリーフ・ケアといいます。
グリーフケアには3つのステップがあります。
- グリーフ(死による深い悲哀)を受け入れる
- 故人との思い出を振り返る
- 新しい自分を見つけるきっかけをつくる
グリーフケアのステップで最も大事なのは、「1.死を受け入れる」です。
これができなければ、後のステップには進めません。
だからこそ、納棺の儀や葬儀は「故人と向き合う時間」として必要なのです。
故人の死を受け入れて悲しみを表現し、それを誰かと分かち合い、
故人がいない社会で生きようとする。その最初の時間なのです。
ただ、災害や事故によって急な別れを経験したような場合、死を受け入れづらくなります。
『だれかの記憶に生きていく』から引用します。
たとえば2011年に起こった東日本大震災。
いまも2000人以上の方が行方不明となっているのですが、
そのご家族はご遺体を目にしていないため、死の実感がわきづらいと言われています。頭では「もうあのひとはいない」とわかっていても、納得できない。
『だれかの記憶に生きていく』著:木村光希,朝日新聞出版,2020/11/20
第一段階である「受け入れ」ができないと、なかなか次に進めないのです
この感覚は、私も経験があります。あまりにも突然な死を経験したとき、
「本当はどこかで生きているんじゃないか」と思ってしまうのです。そう思いたくなる。
こうした場合は、葬儀でなくても、1年を節に同じ気持ちの人が集まったり、
思い出を話し合う場を作るのが良いですね。
そうすることで、悲しみを分かち合って、お互いを支え合うことができます。
今は新型コロナウィルスのせいで1周忌などの集まりもできなくなってしまいましたが、
やはり節目節目で親族や友人が集まることには、グリーフケアの大きな役目があるのです。
今まで僕は、自分の葬儀はいらないと思っていましたが、
グリーフ・ケアの概念を知ってからは、残された人たちのためにも、
必要なことだと思い直しました。
まとめ
今回は、木村光希さんが書いた『だれかの記憶に生きていく』の感想でした。
- 死に向き合い、生き方を考えることが、死生観を磨く
- 具体的には、「死との距離感」と、「自分が何によって憶えられたいか」を意識する
- 死の喪失を受け入れることができなければ、前に進んでいくことができない。
そのために、葬儀や納棺の儀、一定期間ごとの集まりなどの儀式が必要。
ちょうど一年前、僕は一人の友人を亡くしました。
出産の際に亡くなってしまい、「なぜこんなときに……」と悲しみに暮れました。
死を受け入れるのは辛く、しばらくの間は「まだどこかで生きているんじゃないか」と
思っていました。
でもやっぱり、「残された人たちの記憶だけが、自分と世の中をつなぎとめる」とあったように、
死を受け入れて真正面からその意味を考えることが必要なのです。
故人の死から、なにか自分ができることを見つけて生きていくことが大事なのです。
そうすれば、なにか自分も次の世代にできることがあるんじゃないかと、
無事に成長し、もうすぐ1歳になる友人の赤ちゃんの写真を見て思うのでした。
この本に今、出会えて良かったです。