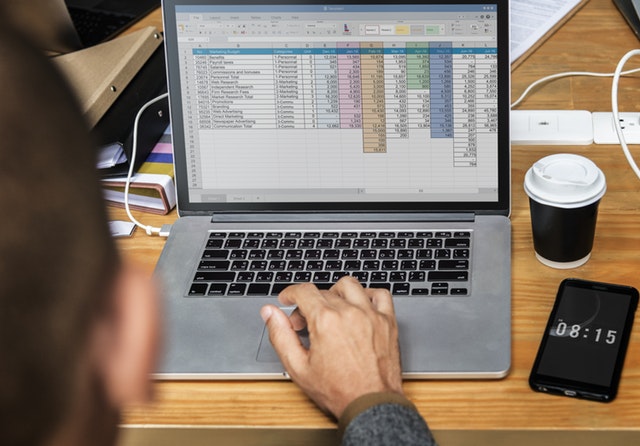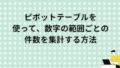子どもの癇癪(かんしゃく)に悩んでいませんか?
お買い物や公園遊びに限らず、家での食事や寝るときまで癇癪を起こされると、どうして良いものか分からずに辛いものがありますよね。
親としても叱れば良いのか、そのまま要求を受け入れて良いのかよく分からず、うまく対応できないまま自分が嫌になってしまいます。
このように対応が難しい子どもの癇癪ですが、適切な対応の仕方があります。先日、このブログでご紹介した『子育てハッピーアドバイス』に記載があり、私もかなり助けられました。
今回も『子育てハッピーアドバイス』から、癇癪への対応方法をお伝えします。
(読んだ内容に僕の解釈を含みます)
大前提!癇癪は悪いことじゃない。
まず癇癪(かんしゃく)とは、「子どもが自分の思い通りにならないときに、激しく泣いたり、
ものを投げたり手足をバタバタさせる行動」です。
一番わかりやすいのは、デパートのおもちゃ売り場で駄々こねるアレです。



一見わがままに見える行動ですが、決してわがままなのではなく、まして悪いことでもありません。これは子どもの心が成長して、「自己主張できるようになった」ということです。
まだ子どもが小さな赤ちゃんだった頃、「ミルクほしい」も「おむつ替えて」もすべて”泣く”という行動で主張してましたよね?あれと似たことです。「おもちゃ買ってほしい!」とか「もっと遊びたい!」ということを「駄々をこねる」という行動で示しています。
ただ、子どもにとって赤ちゃんの頃と違うのは、親が要求を素直に受け入れてくれないことです。
まぁこれは当然で、親としてはすべての要求を受け入れていたら身が持たないわけですが、子どもはそんな事情は知りません。だからこそ、子どもにとっては親が要求を受け入れてくれないというのはよく分からず、悲しいことなのです。
正しい癇癪への対応とは
「癇癪は子どもにとっての自己主張であり、親が要求を受け入れてくれないことは悲しいこと」というのが癇癪の本質でした。
これを前提として癇癪への対応を考えていきます。
やってはいけない1:無視する
一番やってしまいがちな対応ですが、やってはダメです。
一所懸命に自己主張している子どもを無視するのは、「僕/私がこんなに頑張って伝えているのに聞いてもらえないんだ」というメッセージを送っているのと同じです。
これは子どもにとって、とても悲しいことです。
子育てだけでなく対人関係全般に言えることですが、”無視”は絶対にしてはいけません。愛情の反対は無関心です。
やってはいけない2:子どもの要求をすべて受け入れる
子どもの癇癪を避けるために、子供の要求をすべて受け入れるということがありますが、これもよくありません。
正確に言えば、子どもの情緒的な要求は全て受け入れてOKですが、物質的な要求はすべて受け入れてはダメなのです。
癇癪は「〇〇ほしい」とか「〇〇したい」など、物質的な要求を伴う時に起こるのでわかりにくいのですが、本質は「要求しているのに親が分かってくれない、受け入れてくれなくて悲しい」という情緒的なものです。
この情緒的な要求が満たされないまま、物質的な要求を満たし続けると、子どもは情緒を物質で満たそうとします。この傾向は大人まで続き、地位や所有に執着する傾向が強くなります。これは幸せなことではありません。
正しい対応:子どもの気持ちを認めながら、ダメなことはダメと聞かせる
無視するのも要求を受け入れるのもダメならどうすればいいのか。
正しいのは、まず子どもの気持ちを認めてあげることです。
- 「〇〇がほしかったんだね」
- 「〇〇で遊びたかったんだね」
と認めてあげることです。
癇癪は子どもにとって、親が要求を受け入れてくれないのがよく分からず悲しいということの現れでした。だからこそ、まずは子どもの気持ちを汲むことが第一です。同じ目線で話を聞いたり、抱っこをするのも良いでしょう。
よしよしと子どもの気持ちを認め、だんだん落ち着いてきた頃に優しく、ダメな理由を伝えましょう。
子どもにとって「親が自分の気持ちを分かってくれた」という実感があれば、たとえ要求が受け入れてもらえなかったという事実に変わりがなくても、癇癪の前とは子どもの受ける印象が全然違います。
子どもはダメな理由をすぐには理解できませんが、長い時間をかけて「こうした時はダメなんだ」ということを自然に身につけていきます。
「よしよし、〇〇したかったんだね。うんうん。……でも、〇〇だからね。また会いに来ようね。〇〇さん、バイバーイ。」
といった感じで抱っこしながら声をかけてあげましょう。
雰囲気を悪くしないでバイバイする方法
とはいえ、子どもの気持ちを認めながらダメな理由を説明し、円満なままバイバイするというのは至難の技です。
はじめは親もよしよしと聞いていたけれども、子どもの癇癪が収まらず、最終的にむりやり引きずられていく……というのが、よくある光景だと思います。
でも、こうしてしまうと親は「なんでああいうふうに怒っちゃったんだろう」とか「いつもこうなってしまう」とか悩むことになりますし、子どもだって泣いたり怒ったりして終わってしまうので悲しいですよね。
だから、もしその場がうまく収まりそうにない場合は、笑って終わらせることを目指すのが良いです。笑ってその場を終わらせるのに有効な手段はいくつかあります。
- いないいないばぁをする(月齢が低いほど有効)
- こちょがす(オールラウンドに有効)
- 全然違うものに興味を向かせる「見て!あそこに〇〇があるよ!」
特に有効なのは、「全然違うものに興味を向かせる」です。
子どもに限らず、人間は視覚に入ったものに無条件に反応するという習性があります。子どもが「〇〇したい」という時は、単に視界に入ったものに反応しているだけということも多いのです。こうした時はそれほど執着も無いので、新しい視覚情報を入れることによって、それまで興味があったものから離れることができます。
また、これらの手段は組み合わせて使うのも効果的です。
手始めにいないいないばぁ。クスッときたらこちょがして、「ねぇねぇあそこに〇〇があるよ!みて!」と興味を向かせてからもう一回こちょがし、「行ってみよう!」と肩車して離脱……
といったこともできます。
大事なのはその場を笑ってやり過ごすことです。あまり気負わないようにしましょう。
終わりに
今回は『子育てハッピーアドバイス』をヒントに癇癪への対応を考えてみました。
癇癪について大切なことは以下のとおりです。
- 癇癪は、子どもの心が成長して「自己主張できるようになった」ということ。
- 子どもの癇癪に対しては、気持ちを汲みながら、ダメなことはダメと伝える。
- 場が収まりそうに無い時は、笑顔でその場を離脱することを目指す
癇癪は、子どもへの対応の中でも難しいものの一つです。でも、癇癪は子どもの心が成長するために避けて通れない、必要なものです。
だからこそ、親としては精一杯子どもの気持ちを認めてあげましょう。そしてうまくいかなかったからといって、自分を責めたりはしないこと。それが大事です。
『子育てハッピーアドバイス』は子育ての本当に大事な所をライトに読めるのですが、
こうしたよくある悩みにも漫画つきで解説があるので本当にわかりやすいです。
『子育てハッピーアドバイス』が気になる方はリンクを貼っておきますので、
ぜひのぞいてみてください。