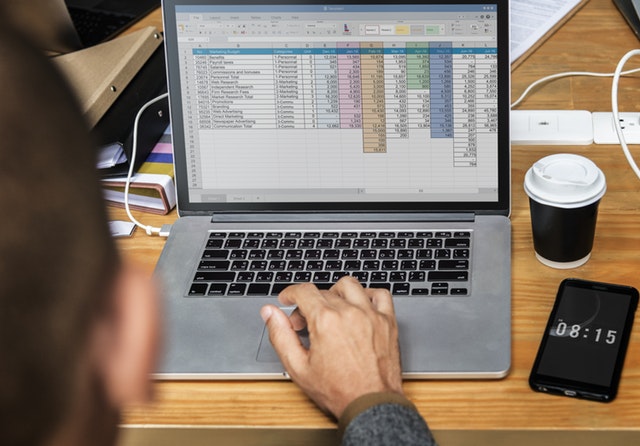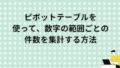子どもはたまに、嘘をつくことがあります。
子育てをしていて子どもの嘘が目立つようになってくると、
「いつも嘘をつくようになってしまうのではないか」
「悪い子になってしまうのではないか」
といったように、親としては大きな悩みになります。
我が家も、3歳半の子どものしつけを始めていますが、まだやってないことを「やった」と言ったり、本当はできることを「できない」と言ったり、小さな嘘が目立つようになってきました。
僕自身も子どもの嘘に対する悩みを抱えていたのですが、大好きな佐々木正美先生の本、
『続 子どもへのまなざし』を読んで、子どもの嘘との付き合い方を学びました。
今回はその一文をご紹介したいと思います。
子どもの嘘は、自分の心を守るため

子どもの嘘を知る上でもっとも大事なことは、
「子どもが嘘をつくのは、子ども自身の心を守るためであること」と理解することです。
子どもがなにか嘘をつく時、その裏返しの気持ちとして「傷つきたくない」とか、
「慰めてほしい」といった気持ちがあります。
それに気がつくことが、親として大切です。
次の文章は、『続 子どもへのまなざし』からの引用です。
子どもばかりではありませんが、なぜうそをつくのかといいますと、自分が傷つきたくないからなんです。
子どもの成長過程で自主性、主体性が芽生えてくるということは、同時に自尊心、誇りという感情も育っているということなんです。
さらに、自分が傷つくという感情もでてきます。ですから、自分が傷つきたくないと思っていると、どうしても、うそが目立ってくるでしょうね。
それは子どもに知恵がついてきたことであり、ある意味では、成長発達のあらわれでもありますから、親は子どものうそをわるいことだと決めつけたり、厳しくしかったりしないほうがいいですね。
うそを奨励するつもりはありませんが、子どものうそに対しては、ある程度は認めてあげるという姿勢がいいと思います
『続 子どもへのまなざし』(P.46)、佐々木正美、福音館書店、2001年
僕は、『続 子どもへのまなざし』のこの文章を読んでから、子どもの嘘をよく観察してみました。
すると、妹(まだ赤ちゃん)にかまっている時に小さな嘘をつくことが多いと気づきました。
これはやはり、「もっと私のことも見てほしい」「まだ私のことも守ってほしい」という気持ちの現れなのです。
この事に気がついてからは、小さな嘘には「はいはい」と答えつつも、「裏にある気持ちも、ちゃんと分かっているよ」というメッセージを送るようにしました。具体的には、ハグをしたり、細かく「愛しているよ」というメッセージを伝えることで、子どもの安心感をケアすることができるようになりました。
気持ちをわかった上で、それでも嘘を叱るとき



嘘が子ども自身の心を守るためにあるといっても、それでも嘘を叱らなければならないときがあります。
それは、「嘘が誰かの心を傷つけるとき」です。
「誰かを傷つけてはならない」という原則だけは、親として、しっかり伝えなければならないことです。「お友達との約束をやぶった」というような、相手が傷つくような嘘があった時だけは、僕も叱るようにしています。
叱るといっても怒ったりはせず、目を合わせて「いけないことだよ」と教えるだけですが、子どもはそれでも分かってくれます。
「自分がいけないことをした」というのは、子ども自身が一番わかっていたりします。
大人でも、誰かの気持ちを守るために嘘をつくことがあります。
嘘自体は悪いことではなく、むしろ、人間が生きていくためになくてはならない、コミュニケーションの一つです。問題は、それが人を傷つけるかどうかです。
「人を傷つけない」という原則が守れるのであれば、子どもの嘘に対しては、子ども自身の気持ちを守ってあげるのが良いんじゃないかと思います。