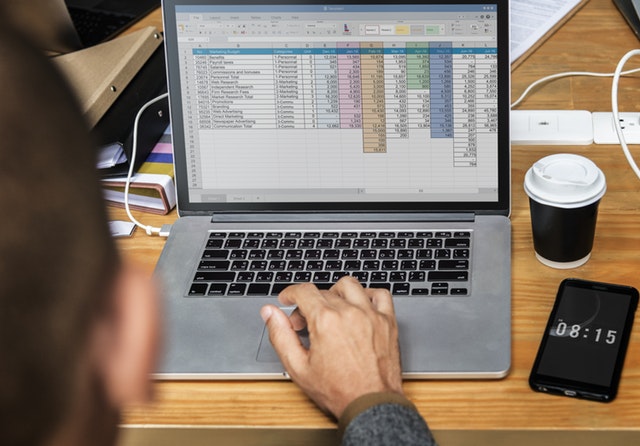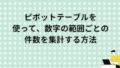『業務改善の問題地図』の感想です。
- 業務改善の目的は、正しく変われる組織になること
- 働き方改革のゴールは、ビジネスモデル変革
- 業務改善はまず、現場が声を出せるようにするところから
- ツールの導入前には、ECRSで業務を整理する
業務改善を実際に進めようとすると、いくつもの問題にぶち当たることになります。
- 「現場が悩んでいることがあるのに、それが声として出てこない」
- 「悩んでいる担当者に詳しく聞こうとしても、忙しくて時間を割いてもらえない」
- 「重要なシステムを、現場を知らない人間が決めてしまう」
- 「最初は現場もやる気だったのに、何も変わらないまま時間が経ってしまった」
- 「業務改善といっても、そもそも何をすれば良いのかわからない」
僕自身、2年前に初めて業務改善プロジェクトに参加して、
上記のような問題にあたり続けてきました。
これらの問題の厄介なところは、業務改善の過程で必ず何かしらの問題は起こり、
業務改善の経験があるメンバーがいない限り、誰もこの問題への対処法を知らないことです。
働き方改革によって、社会的にも業務改善の機運は高まっていますが、
これらの問題に阻まれて目的を達成できなかったプロジェクトは
かなりの数、あるんじゃないかと思います。
せっかく機運が高まっているのに、これはすごくもったいない。
僕自身、改めてこうした問題に正しく向き合いたいと思い、
『業務改善の問題地図』(著:沢渡あまねさん、元山文菜さん)を読みました。
こちらの本ですが、業務改善の目的をしっかり示した上で、
担当者がぶち当たりやすい問題を広く網羅した内容になっているので、非常に参考になります。
問題がどういう時、どんな立場の人に起こりやすいかを知っているだけでも、
現場のコミュニケーションの質が変わリます。
今回はこの本から、僕が特に大事だと思ったところを紹介します!
業務改善の目的と、働き方改革のゴール

業務改善について、まず知っておきたいこと。
それは、「業務改善」の目的は正しく変わることのできる組織になることであり、
業務改善はその目的を達成するための手段であるということです。
正しく変わることができる、というのは、環境の変化に対して、
組織のメンバーが自主的に仕事のやり方を変えることができるということです。
仕事のやり方を変えると一言にいっても、実際には以下のようなことが必要です。
- ビジネスモデルやビジネスプロセスを変える
- ビジョン、ミッションを再確認する
- 意思決定プロセスを変える
- 煩雑な事務手続きを削減する
- 部門のコミュニケーションのあり方を変える
- 情報システムを最新化する
これだけのことを、自主的に変えていく。
そうした高い自主性と問題解決能力、スキルをもって、
最終的にはビジネスモデルを改革できるようになること。
そして、現場の人間がプロフェッショナルとして活躍できる場を作るのが、
「働き方改革」の大きなゴールとなります。
「業務改善」も「働き方改革」もビッグワードすぎて、人によってそのイメージもバラバラです。
この「業務改善の目的」と「働き方改革のゴール」を示している点に、
本書の大きな意義があります。
業務改善は現場が声をあげられるようにすることから



では、具体的にどうやって業務改善を行っていくのか。
まず、定例会や会議にKPTを取り入れること。KPTとは、
- Keep(良かったこと)
- Problem(問題だと思うこと)
- Try(試してみたいこと)
といった3つの軸を使って、それまでやってきたことを定期的に振り返るフレームワークのことです。
KPTについては、この記事がわかりやすいです。
KPTに限らず、「書き出す」という行動は、情報をフラットにするうえで非常に効果があります。
会議ではなかなか言いづらいことも、見える化≒言える化となり、共有することができるのです。
業務改善が進みにくい組織は多くの場合、現場が声を出せない雰囲気があるので、
書き出すことで少しずつ言える範囲を増やしていくことが重要です。
また、トップの側も業務改善を本気で進めたいなら、改善の必要性を「自分の言葉」で何度も語る必要があります。「業務改善のその先」で何を叶えたいのか、それを明確にすることも大事です。
新たなビジネスモデルでの成功なのか、従業員の幸福と自己実現なのか。
改善を進めようとする時に、「業務改善のその先」の視点が抜けているケースは非常に多いです。
この視点が抜けると、現場の人間は「改善したらその分また仕事が増える……」と考えちゃうかもしれません(改善あるあるです)。
もしこう考えたら、現場の人間がやる気を出すなんて難しいですよね。
もちろん、改善を率先する人・チームを激励し、評価にも反映することも欠かせません。
そして、改善を一個の仕事として見つめ、改善を推進するチームに権限とリソースを与えること。
業務改善は社外の情報を常に集めなければなりませんし、動く時は迅速に動かなければなりません。
裁量が感じられないまま改善の仕事をするのは、非常に厳しいものがあります。
ツールの導入前に、ECRSで業務を整理



組織の中で問題意識が明らかになってくると、その後はツール導入のステップになります。
ツールは今、非常に魅力的なものが多いです。
僕も大好きkintoneをはじめとして、Salesforce、smartHRなど、業種別・職種別に数え切れないくらいのソリューションがあります。
また、こうしたパッケージでは収まりきらない場合は、システム外注します。
でも、こうしたツールやシステムを導入する前に、自分たちが行っている業務を整理しなければなりません。この整理をおろそかにすると、「導入したけど現場が使ってくれない」とか、「そもそもシステムがうちの業務にあっていなかった」といったシステム導入の失敗につながって、とんでもない損害を生むことになりかねません。
本書の後半では、業務の棚卸表などを使って業務を整理・問題解決の優先度をつけていくのですが、その中でも、ECRS(イクルス)が非常に大事です。
ECRS(イクルス)とは、業務を減らすためのフレームワークで、
- Eliminate(廃止)……仕事自体をなくす
- Combine (結合)……ほかの仕事と同時にする
- Rearrange(入替と代替)……仕事の順番や担当者を入れ替える
- Simplify(シンプルに)
という4つの観点から業務を評価します。
ELIMINATE(廃止)が一番効果があるので、最初にELIMINATE(廃止)から考えていきます。
例えば、稟議書に決裁者がハンコを押す業務。この押印をなくせないかと考えてみる。
もし無くせるならそれだけでその分の作業がなくなりますし、もし無くせないなら次は、他の業務とCombine (結合)できないか考える。この場合は、「他の押印作業の時に、稟議書にも押印する」といった感じでしょうか。
ちなみに、僕自身も1年前、業務改善に取り組んでいた時にこのフレームワークが役に立ちました。
ネックとなっていた作業を半分の時間でやろうと考えていた時、ある作業の前後を入れ替える(Combine)ことで、チェック作業にかかる時間が激減し、半分の時間で完了できるようになりました。
おわりに
今回は、『業務改善の問題地図』の感想を書きました。
- 業務改善の目的は、正しく変われる組織になること
- 働き方改革のゴールは、ビジネスモデル変革
- 業務改善はまず、現場が声を出せるようにするところから
- ツールの導入前には、ECRSで業務を整理する
「業務改善にはどんな意義があるのか」
「業務改善は、どんな問題が立ちふさがってくるのか」
「業務の整理はどうやってやればいいのか」
業務改善を進める中で、担当者が悩む問題を大きく捉えつつも、絶対に必要なところは外さずにポイントをまとめ上げた良書だと率直に感じました。まさに地図。
僕も2年前にこの本に出会っていたら、もっとうまく業務改善できたのかな~と思いました。
これから業務改善に関わる人、業務改善をもっと深く知りたい人にオススメです!