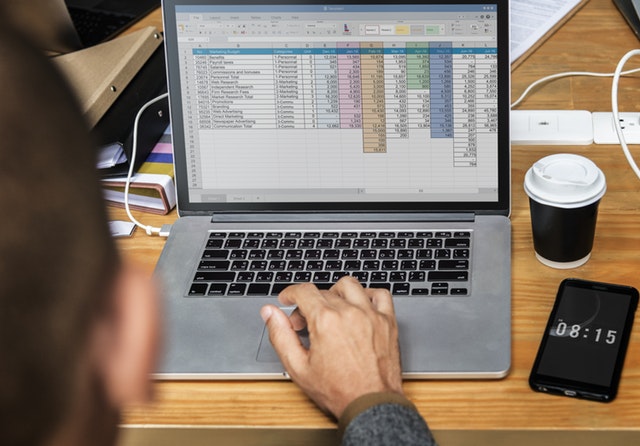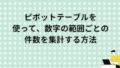Gunosyの創業者、福島良典さんが書いた『センスのいらない経営』から、「これからのテクノロジーの進化と経営はどのように付き合っていくべきか」「一人の人材として、どのような姿勢をとっていくべきか」について紹介。
- テクノロジーで効果を生むためには、経営者自身が、機械に与えるべき適切な目標を押さえなければならない。
- ビジネスとして成功するプロダクトを作るには、自分たちの作りたいものと、社会との接地面を探し続ける必要がある。
- 取るべきリスクを取る度胸と、どう転んでも致命的にならないように外堀を埋めるバランス良さが経営者には必要。
こんにちは、おぎです。
あなたは普段、テクノロジーとどのように付き合っていますか?
会社員であっても経営者であっても、もはやテクノロジーの進化と無縁ではいられません。
普段、テクノロジーを身近に感じていない方でも、テクノロジーの影響を知っているのとそうでないのでは、これからを生き抜く人材としての力に大きく関わりそうです。
あなたもその影響力を、ひしひしと感じているのではないでしょうか?
私もこの影響力に対抗する方法を模索している一人ですが、最近読んだ本がこの点に答えてくれていましたので、あなたにも紹介したいと思います。
今回は、Gunosyの創業者、福島良典さんが書いた『センスのいらない経営』から、「これからのテクノロジーの進化と経営はどのように付き合っていくべきか」「一人の人材として、どのような姿勢をとっていくべきか」について紹介したいと思います。
この本は、「不確実性の高い社会で、どのようにビジネスを展開すれば良いのか、”テクノロジー”という軸に沿って語る本」です。
著者の福島さん自身が最先端テクノロジーに詳しいエンジニアということもあり、あなたがテクノロジーとの付き合い方に不安を感じているなら、参考になるはずです。
それでは紹介していきます!
テクノロジーと経営の付き合い方

福島さんは、「データや人工知能に注目する経営者は多いが、それを通してどのような目的を達成しようとしているのかを理解していないと、効果はない」と言います。
大前提として、機械は与えられた命令を正確にこなし、最大の効果で出力します。
しかし、誤った目的を設定すれば、誤った結果が最大で出力されるだけです。本書の例では、「記事のクリック率を上げる」と単に命令しただけでは、釣り広告やフェイクニュースばかりが上位にでてきてしまったそうです。



僕もこれは覚えがあって、Excelのマクロを作っていたときに、誤った結果を大量に出力したことがあります😅
テクノロジーをうまく使うには、適切な目的を機械に与えてあげる必要があります。
最終的な目標を細かく砕いて、「いつまでに、どの媒体で、どれくらいの出力であれば成功と言えるのか」といった基準を機械に与えるのです。そしてこれは、人間にしかできないことです。
人間が適切な目標を機械に与え、機械が最大出力することで、最大の効果を生むことができます。
経営者は、この適切な目標設定を常に押さえておかなければなりません。
この考え方が無ければ、いくら便利なツールを導入したとしても、効果を生むことはできません。
伸びるプロダクトの特徴



革新的でイケてるテクノロジーが生まれたとしても、それ自体は事業として成功するプロダクトにはなりません。
福島さんは、「ユーザーが求めている社会的課題と、テクノロジーのトレンドが合致すると伸びるプロダクトが生まれる」と言います。
福島さんが開発したGunosy自体もそうです。
Gunosyは、福島さんが「欲しい情報が飛び込んでくる」ニュースアプリを目指して作ったものです。
福島さんのニーズは、社会的なニーズにも合致していました。
自分たちがいくら好きでワクワクするものでも、社会との接地面が無いと受け入れられません。
ビジネスとして成功するプロダクトを作るには、自分たちの作りたいものと、社会との接地面を探し続ける必要があります。
これはプロダクトが成功した後も変わりません。
社会のニーズを常に探し続けることで、「イノベーションのジレンマ」を避けることができます。
プロダクトの検証とリスクコントロール



成功するプロダクトを生むためには、大量の実験が必要です。
とにかく大量に、すばやい決断をして、行動の結果が良くなったのか悪かったのか、検証し続けます。
Gunosyではこの姿勢を非常に重視していて、大量に実験し、検証を重ねる社員を優先的に評価しています。
こういう聞くと、「実験に失敗した時の損失はどうするんだ」と気になる経営者がいると思います。
これについて福島さんは「実験結果はわからなくても、リスクはコントロールできる」と言います。
例えばアプリに実験的な機能を追加するにしても、最初からすべてのユーザーを対象にしない。
狭い範囲で反応をみて、良さそうだったら広げていくという手順を踏みます。
一見、当たり前に思えることですが、「サービスのデザインをいきなり変更する」「新商品のテレビ広告をいきなり全国規模で出す」といったような話をあなたも聞いたことがあるのではないでしょうか?
効果が分からないのであれば、常にリスクは低くするべきです。
「取るべきリスクを取る度胸と、どう転んでも致命的にならないように外堀を埋めるバランス良さが経営者には必要」とも、福島さんは言います。
一人の人材としての、テクノロジーの進化との向き合い方
ここまでに書いてきたことを一旦整理しましょう。
・テクノロジーで効果を生むためには、機械に与えるべき適切な目標を押さえなければならない。
・ビジネスとして成功するプロダクトを作るには、自分たちの作りたいものと、社会との接地面を探し続ける必要がある。
・取るべきリスクを取る度胸と、どう転んでも致命的にならないように外堀を埋めるバランス良さが必要。



これらを実践できる人材であるために必要なことは、次のとおりです。
- 大量の決断をすること
- 決断は素早く行うこと
- 実験した後、必ず検証を行うこと
- テクノロジーを理解し、身近な課題にあてはめて解決できること
本書ではこうした人材のことを、「エンジニア的人材」と呼びます。
テクノロジーが絶えず進化する中で必要なのは、この「エンジニア的人材」です。
すばやい決断に関して面白いと思ったのは、Amazonでは70%の情報が出揃ったら決断をするそうです。正しい判断基準を持っていれば、70%の情報が出揃ったところで良いか悪いかという判断はつきます。
判断ができなかったり、「まだ情報が足りない」と判断を先送りしてしまうのは、判断基準が明確になっていないからです。「機械に目的を与える」のと同じように、自分の中での判断基準を常に押さえておくことが大事です。
また、Gunosyでは検証をしやすくするために、検証のテンプレートが用意されているそうです。
このテンプレートがあれば誰でも同じ目線でチェックをすることができ、テンプレートが埋まっているかどうかで「検証したかどうか」ということがわかるので、「検証する文化」を根付かせることができています。
AIの進化にともなって、事務職をはじめ、弁護士や医師といった専門職ですら、AIによって代替可能と言われています。人間の身に付けることができるスキルの多くは、機械もできるようになっていきます。
それを踏まえた上で、「”自分は何をしたらいいか”を常に考え続ける。そうした姿勢を持つことが、本当の意味で自分を活かす」と福島さんは言います。
大切なことはテクノロジーの進化にただ流されるのではなく、テクノロジーを理解しようとし、流行りのトレンドの中からどれがこれからのメインストリームになるのかを見極める力です。



おわりに
今回はGunosyの創業者、福島良典さんが書いた『センスのいらない経営』から、「テクノロジーの進化と経営の付き合い方」「一人の人材としてどのような姿勢をとっていくべきか」について紹介しました。
「これからのテクノロジーの進化と経営はどのように付き合っていくべきか」
- テクノロジーで効果を生むためには、経営者自身が、機械に与えるべき適切な目標を押さえなければならない。
- ビジネスとして成功するプロダクトを作るには、自分たちの作りたいものと、社会との接地面を探し続ける必要がある。
- 取るべきリスクを取る度胸と、どう転んでも致命的にならないように外堀を埋めるバランス良さが経営者には必要。
「一人の人材として、どのような姿勢をとっていくべきか」
- 大量の決断をすること
- 決断は素早く行うこと(判断基準をもつ。70の情報で判断する)
- 実験した後、必ず検証を行うこと(テンプレートをもつ)
- テクノロジーを理解し、身近な課題にあてはめて解決できるスキルを身につける
いかがでしたでしょうか?
こうした経営を行うことや、人材を目指すことを少し重く感じているでしょうか?
僕も最初はそう感じました。
こうした人材にすぐなれるわけではありませんが、普段からプログラミングの考え方を勉強してみたり、最新のテクノロジーがどのような仕組みで動くのか、アルゴリズムを勉強することは大いに役立ちます。
僕自身、Excelのマクロを作ってみたり、サイボウズのkintoneを作ることに取り組んでいく中で、こうしたことを勉強して、少しずつ見につけていきました。
プログラミングの考え方やアルゴリズムには、これまで常識とされてきた考え方よりも圧倒的に効率的な知恵が含まれています。一見、テクノロジーに関係のない仕事でも、プログラミングの考え方を応用することで圧倒的な成果をあげることができたりします。
あなたが、もしこうした機会をあまり経験をしていないなら、飛躍できるチャンスです。
最後に、僕のオススメ書籍を紹介しておきます。『センスのいらない経営』と共に読んでみてください。
ではまた。