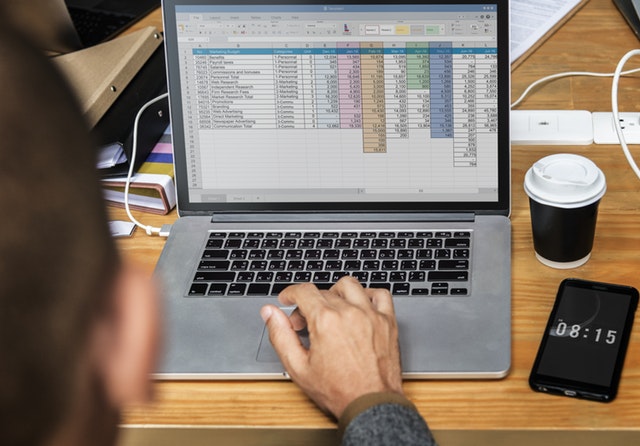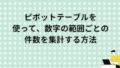飯田祐基さんの本、『バズる動画・ライブ配信 確実に拡散するしくみ』から、「拡散される動画やライブ配信をどうやって生み出すか」について紹介します。
- 動画は拡散を前提に作る!拡散されないのは、「前を通らないと気づいてもらえない飲食店」と同じ!
- 動画は質よりも量。定期的に動画を投稿し、タイトルに馴染みのない言葉は使わず、サムネイルはターゲットの心に一瞬で引っかかる画像や文字を入れる。
- 分析は、「離脱地点」のように「ダメな所」に注目する。
こんにちは、おぎです!
今日は飯田祐基さんが書いた『バズる動画・ライブ配信 確実に拡散するしくみ』を読んで大事だと思ったところをまとめます!
この本は動画とライブ配信について、「拡散されること」を前提にコンテンツを作る方法、人気チャンネルを作る方法、インフルエンサーマーケティングの効果を上げる方法について解説した本です。
「動画の作り方」の本はたくさんありますが、「拡散する」という視点で書かれているのは少ないです。

動画クリエイターが悩むのは動画の作り方よりも、「作った後に見てもらえない」「どうしたらもっと多くの人に見てもらえるようになるのか」といったことで悩む方が多いのではないでしょうか?
この本は、その悩みに間違いなく答えてくれる本です。
実際の所、飯田さんは株式会社ライバー(メイン事業がライブ配信 https://livestreamers.co.jp/ )の創業者ということもあり、書いてあることの説得力は抜群です😄。
それでは、本書で大事だと思ったところをまとめていきます。
動画は拡散を前提に作る



まず大前提ですが、動画は「拡散することを前提に」作ります。
普通の人は、動画を作ってから拡散することを考えることが多いですが、実は動画を見てもらえるかどうかは、動画の内容よりも、タイトルやサムネイル、SNSで共有された時の印象で決まることが多いのです。
「SNSで拡散されるとしたら、どんなタイトルで、どういうターゲットに見てもらいたいか」といった考えの元に動画を作らないと、ターゲットに見てもらいにくくなり、冒頭のような「作ったのに見てもらえない」といった悩みにつながってしまいます。
飲食店で言えば、店名や店の外観でしょうか。最初から拡散することを前提に店名や外観を決めているのと、そうでないのでは、お客さんに与える印象が全く違うことはお分かりいただけますね?
もちろん中身が伴っていないとダメですが、中身に入る前の店名や外観で損をしている飲食店が多いことは、なんとなく感じてもらえているのではないかと思います。
「拡散を前提に作る」というのは動画だけでなく、飲食店やエンジニア、出版……どの業界でも必要な考え方です。
では、拡散を前提とした動画はどのように作れば良いのでしょうか?
動画は質よりも量



動画は質よりも量を重視します。
動画は24時間いつでも視聴され、拡散されていきます。動画数が10本のチャンネルと100本のチャンネルでは、拡散される可能性が段違いです。とにかく量を重ねていくことが、圧倒的な結果につながります。
「絶対にバズる動画は無いが、絶対にバズらない動画はたくさんある。」と飯田さんは言います。
動画がバズるかどうかは誰も分かりませんが、量が多ければ多いほどその可能性は上がります。
バズった動画を研究しながら自分の動画を作り、あーでもないこーでもないと動画作りの検証を重ねることで、バズる可能性を秘めた動画を作ることができます。
こう書くと「動画数が少ないうちは、大物YOUTUBERに勝てないの?」と思われるかもしれません。
安心してください。ちゃんと本書では、動画数が少ないときに取れる戦略を紹介しています。
その戦略についてはこの記事では割愛させていただきますので、ぜひ本書を読んでいただきたいです。
とはいえ、その戦略を取るためにも、動画の量を稼いでいくことや、この後に紹介するような工夫は絶対に必要です。
HHH(スリーエイチ)戦略を使いこなす



動画を作っていくと直面するのが、「どんな動画を作れば良いのかわからなくなる」という問題です。
これには、Googleが提唱しているHHH(スリーエイチ)戦略が参考になります。
- HELP ……いわゆるハウツー系の、ためになる動画。新規視聴者の獲得に有効。
- HUB ……新製品紹介や、キャンペーン告知など。チャンネル登録者向けのコンテンツ。
- HERO……ニュースサイトやSNSなど、プラットフォーム外からの流入コンテンツ。いわゆるバズ。
HELPコンテンツでチャンネル登録者を獲得し、HUBコンテンツでチャンネル登録者を飽きさせないというのが主な戦略です。HEROコンテンツのようなバズや、コラボ動画などで外部からの流入を得ることができれば、チャンネルが大きく成長します。
HHH戦略はYouTubeの運営元であるGoogleが提唱している戦略ということもあって、重要性の高い戦略です。どんな動画を作ればいいか迷ったときは、この戦略を元に動画を内容を決めてみてはいかがでしょうか?
サムネイルに、ターゲットの心に一瞬で引っかかるものを入れる



動画を見てもらえるかどうかを決める重要な要素にサムネイルがあります。
極論、クリックしてもらえるかどうかはサムネイルにかかっていると言っても過言ではありません。
この点について、「ターゲットの心に一瞬で引っかかるもの(画像、文字)を入れる」と飯田さんは言います。
視聴者がYouTubeのトップ画面などで動画を探している時、その心の中には気になっていることや、調べたいことが秘められています。
「今度、子どもにプレゼントしようと思っている玩具」
「新しく試してみようと思っている、ランニングシューズ」
「家族で行こうと思っている、旅行先のアトラクション」
人によってその内容は違いますが、これらを考えている時、目の前にその気になるものの画像や文字が飛び込んできたら、ついクリックしてしまいませんか?誰でもクリックすると思います。
だからこそ、サムネイルには玩具やランニングシューズの画像、アトラクションの文字を入れることが大事です。「ターゲットの心に一瞬で引っかかるものを入れる」というのはこういうことです。
タイトルには馴染みのない言葉は使わない



タイトルをつける上で迷うことの一つに「新製品の商品名などを入れるかどうか」という問題がありますが、結論からいえば入れない方が良いです。
この点について飯田さんは「馴染みのない言葉は使わない」と言います。商品やサービス名を知らない視聴者でも、気になるタイトルにする方が良いです。
例えばチョコレートの新商品をPRするとして、「(新商品タイトル)のレポート」のようなタイトルでは、新商品を知らない人は見ようとしません。
これを「〇〇配合のチョコレートの驚きの効果!今までのチョコにない効能とは?」といったタイトルにすれば、新商品を知らない人でも、健康や美容に興味がある人にクリックしてもらえます。
誰でも理解できる、馴染みのある言葉を使ってタイトルをつけることで、より多くの人に見てもらうことができます。
分析は「ダメな所」を見る



動画を投稿した後は、必ず分析を行います。
分析では、「総再生回数」「チャンネル登録数」「SNSでの共有数」をチェックしますが、それに加えて重要なのが「離脱時間」や「維持率」のような「ダメな所」に注目することです。
これらのダメな所はそのまま「改善の種」になります。
離脱時間の前でテンポが悪いところがあれば、その部分の構成を変えてみたり、思い切ってジェットカットするのもいいです。維持率が悪ければ、同じ内容が繰り返されていてくどい内容になっているのかもしれません。とにかく、離脱時間や維持率には改善できる要素が詰まっています。
こうした改善点を見つけて、バズっている動画の内容と比較してみることで、自分の動画作りのスキルが上がっていきます。どんどん検証していきましょう。
おわりに
今回は飯田祐基さんの本『バズる動画・ライブ配信 確実に拡散するしくみ』から、大事だと思ったところを紹介しました。









いかがでしたでしょうか?
本書は以前から気になっていた本でしたが、実際に読んでみて、ビジネスで大切な考え方を紹介している内容だと改めて思いました。ライブ配信を事業とした方ならではの、ノウハウが詰まった本です。
この記事で紹介したのは本書のごく一部です。
- 動画本数が少ないチャンネルが取れる戦略
- 動画の長さはどれくらいがベストか
- クリエイターやライバーに求められる能力
- チャンネルのトップ画面にはどんな動画を置くべきか
- インフルエンサーをマーケティングに活用するにはどうすればいいか
といったように、細かい疑問にも答えてくれる良書です。動画クリエイターだけでなく、企業のマーケティング担当者にもオススメの本です。本書の内容が気になったら、ぜひ読んでみてください!